4dsの波動とメタトロンの波動が心臓の右心室か、右心房まで一致、膵頭、膵尾まで一致する
この投稿をInstagramで見るKazuo Hori(@horik75)がシェアした投稿 – 2020年Jan月29日am6時08分PST
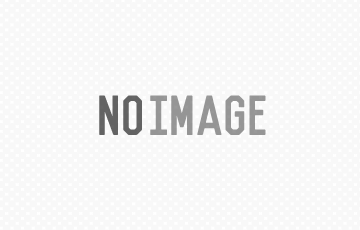 未分類
未分類
この投稿をInstagramで見るKazuo Hori(@horik75)がシェアした投稿 – 2020年Jan月29日am6時08分PST
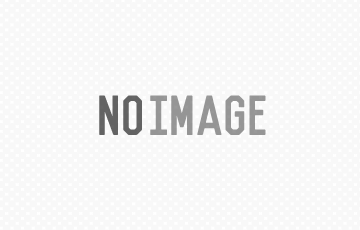 未分類
未分類
この投稿をInstagramで見るKazuo Hori(@horik75)がシェアした投稿 – 2020年Jan月28日pm10時26分PST
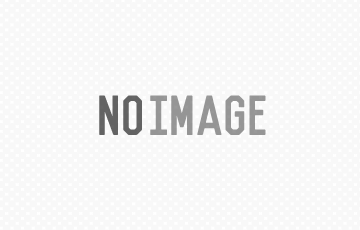 未分類
未分類
20代前半まではあんなにスリムで細かったのに40歳にもなるとなんでこんなに巨大化したのかしら?
と、思い当たる人は多いと思います。 ただ単に、脂肪があなたを太らせたわけではないのです。 骨格があなたを太らせたのです。 年齢と共に胸腔、腹腔は膨張していきます。
20代のころはきゃしゃだった胸板が、 男性みたい胸板が厚くなっていませんか? それは胸腔が拡がり肋骨が拡がっていったからです。 背筋を伸ばして胸を張ると、必然的に肋骨は拡がります。
そして、腹腔、胸腔は拡がりそこにはスペースができます。 そこに脂肪がたまったり内臓がむくむスペースを作るのです。 生物や宇宙も同じようなエイジングをたどります。
チュウリップで言うと蕾のころは10代で、どんどん広がっていき、一番きれいなチュウリップ時期が人間でいう20代のころです。
そこから花弁は拡がっていき人間でいう中年の時期になります。 人間の胸郭で例えると、20代のころは胸郭は狭かったのですが年齢と共に胸郭、すなわち肋骨は拡がっていくのです。
50代にもなれば20代の時はスリムだった胸郭も広がってがっちりしていきます。
チュウリップも広がりすぎると枯れて、最後は種だけが残ります。 人間の拡がり過ぎたった胸郭も、死ぬ間際になると、痩せ細って、最後には死を迎え骸骨になります。
宇宙も同じく、銀河系は成長期は防虫していきます。ある日広がりすぎるとビッグバーンが起こり、爆発し銀河系は消滅しブラックホールになるでしょう。 最終的に人間は死ぬのですが、より健康に美しく生きるには、胸腔、腹腔を狭め減腔を意識する必要があります。
ゲンクウをすることでアンチエージングと健康が保たれます。
美肌効果 2章10 スリムなウエスト 内臓機能UP 6章2 肥満防止 血圧、血糖値を下げる 6章2
>>>>>>セミナー情報<<<<<<<<<
東京 2月16日
■4DS新着情報
(4DSとは?)
(姿勢革命とは?)
(減腔とは?)
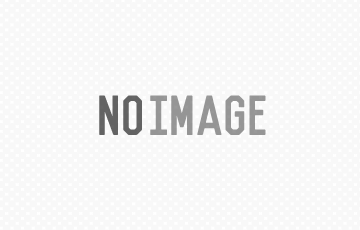 未分類
未分類
背筋を伸ばし胸を張ると、腹腔、胸腔が広くなります。
胸腔腹腔が広くなるとそこには余分なスペースが生まれます。
そのスペースを埋めるために内臓脂肪がたまったり、
内蔵がむくみやすくなったりします。
また、腸に対する圧も下がり便秘になりやすかったりもします。
腹膜などの間質(内臓と内臓をつな臓器)にも、リンパ液が溜まり浮腫みやすくなります。
内蔵や間質がむくめば、全身のリンパも循環不良を起こします。
全身のリンパ液はリンパ管を通して循環しますが内蔵がむくむと、腹部のリンパ管が渋滞を起こして、全身のリンパの循環が悪くなり、顔や足がむくむ原因にもなります。
心臓の負担を減らし、リンパ液の循環を良くするためにも、脱力しては胸腔腹腔を潰しましょう♪
>>>>>>セミナー情報<<<<<<<<<
東京 2月16日
■4DS新着情報
(4DSとは?)
(姿勢革命とは?)
(減腔とは?)
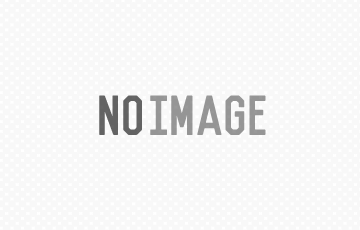 未分類
未分類
背筋を伸ばし胸を張ると、腹腔、胸腔が広くなります。
胸腔腹腔が広くなるとそこには余分なスペースが生まれます。
そのスペースを埋めるために内臓脂肪がたまったり、
内蔵がむくみやすくなったりします。
また、腸に対する圧も下がり便秘になりやすかったりもします。
腹膜などの間質(内臓と内臓をつな臓器)にも、リンパ液が溜まり浮腫みやすくなります。
内蔵や間質がむくめば、全身のリンパも循環不良を起こします。
全身のリンパ液はリンパ管を通して循環しますが内蔵がむくむと、腹部のリンパ管が渋滞を起こして、全身のリンパの循環が悪くなり、顔や足がむくむ原因にもなります。
心臓の負担を減らし、リンパ液の循環を良くするためにも、脱力しては胸腔腹腔を潰しましょう♪
>>>>>>セミナー情報<<<<<<<<<
東京 2月16日
■4DS新着情報
(4DSとは?)
(姿勢革命とは?)
(減腔とは?)
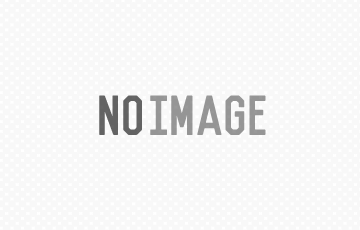 未分類
未分類
背筋を伸ばし胸を張ると、腹腔、胸腔が広くなります。
胸腔腹腔が広くなるとそこには余分なスペースが生まれます。
そのスペースを埋めるために内臓脂肪がたまったり、
内蔵がむくみやすくなったりします。
また、腸に対する圧も下がり便秘になりやすかったりもします。
腹膜などの間質(内臓と内臓をつな臓器)にも、リンパ液が溜まり浮腫みやすくなります。
内蔵や間質がむくめば、全身のリンパも循環不良を起こします。
全身のリンパ液はリンパ管を通して循環しますが内蔵がむくむと、腹部のリンパ管が渋滞を起こして、全身のリンパの循環が悪くなり、顔や足がむくむ原因にもなります。
心臓の負担を減らし、リンパ液の循環を良くするためにも、脱力しては胸腔腹腔を潰しましょう♪
>>>>>>セミナー情報<<<<<<<<<
東京 2月16日
■4DS新着情報
(4DSとは?)
(姿勢革命とは?)
(減腔とは?)
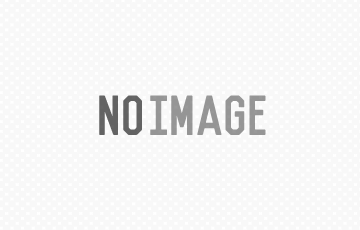 未分類
未分類
背筋を伸ばし胸を張ると、交感神経優位になると何遍も言っています。
交感神経優位になると、内臓だけでなく、皮膚への血流が悪くなるのです。
交感神経は「闘争と逃走」の自律神経と言われています。
交感神経優位だと、皮膚表面の欠陥が細くなり、喧嘩でケガした時も出血が抑えられます。
その分、筋肉に血流が多くいくので、内臓への血流は量は低下します。
また、背筋を伸ばし胸を張ると横隔膜の動きも悪くなります。
構造的には背筋を伸ばし胸を張ると、下部胸郭のくびれがなくなります。そして横隔膜は横に広がり呼吸をするときの横隔膜の上下する動きが小さくなります。
横隔膜には大動脈、大静脈が貫通しています。
心臓がポンプして、血液を全身に循環させるように、
横隔膜の上下の運動もポンプのような機能を持ち、心臓の手助けをしています。
第二の心臓は脚!!と言われていますが、脚は歩いてないとポンプの役割を果たしません。
しかし、横隔膜は呼吸をするたびに動きますので、寝てるときも起きてるときも心臓のように血液のポンプを手伝っています。
そう、第二の心臓は脚ではなく、横隔膜なのです♪
>>>>>>セミナー情報<<<<<<<<<
東京 2月16日
■4DS新着情報
(4DSとは?)
(姿勢革命とは?)
(減腔とは?)
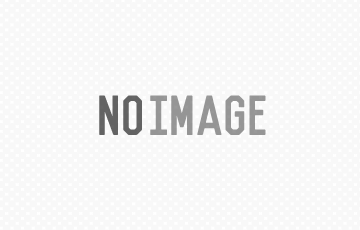 未分類
未分類
背筋を伸ばし胸を張ると、交感神経優位になると何遍も言っています。
交感神経優位になると、内臓だけでなく、皮膚への血流が悪くなるのです。
交感神経は「闘争と逃走」の自律神経と言われています。
交感神経優位だと、皮膚表面の欠陥が細くなり、喧嘩でケガした時も出血が抑えられます。
その分、筋肉に血流が多くいくので、内臓への血流は量は低下します。
また、背筋を伸ばし胸を張ると横隔膜の動きも悪くなります。
構造的には背筋を伸ばし胸を張ると、下部胸郭のくびれがなくなります。そして横隔膜は横に広がり呼吸をするときの横隔膜の上下する動きが小さくなります。
横隔膜には大動脈、大静脈が貫通しています。
心臓がポンプして、血液を全身に循環させるように、
横隔膜の上下の運動もポンプのような機能を持ち、心臓の手助けをしています。
第二の心臓は脚!!と言われていますが、脚は歩いてないとポンプの役割を果たしません。
しかし、横隔膜は呼吸をするたびに動きますので、寝てるときも起きてるときも心臓のように血液のポンプを手伝っています。
そう、第二の心臓は脚ではなく、横隔膜なのです♪
>>>>>>セミナー情報<<<<<<<<<
東京 2月16日
■4DS新着情報
(4DSとは?)
(姿勢革命とは?)
(減腔とは?)
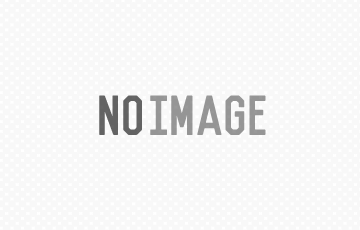 未分類
未分類
背筋を伸ばし胸を張ると、交感神経優位になると何遍も言っています。
交感神経優位になると、内臓だけでなく、皮膚への血流が悪くなるのです。
交感神経は「闘争と逃走」の自律神経と言われています。
交感神経優位だと、皮膚表面の欠陥が細くなり、喧嘩でケガした時も出血が抑えられます。
その分、筋肉に血流が多くいくので、内臓への血流は量は低下します。
また、背筋を伸ばし胸を張ると横隔膜の動きも悪くなります。
構造的には背筋を伸ばし胸を張ると、下部胸郭のくびれがなくなります。そして横隔膜は横に広がり呼吸をするときの横隔膜の上下する動きが小さくなります。
横隔膜には大動脈、大静脈が貫通しています。
心臓がポンプして、血液を全身に循環させるように、
横隔膜の上下の運動もポンプのような機能を持ち、心臓の手助けをしています。
第二の心臓は脚!!と言われていますが、脚は歩いてないとポンプの役割を果たしません。
しかし、横隔膜は呼吸をするたびに動きますので、寝てるときも起きてるときも心臓のように血液のポンプを手伝っています。
そう、第二の心臓は脚ではなく、横隔膜なのです♪
>>>>>>セミナー情報<<<<<<<<<
東京 2月16日
■4DS新着情報
(4DSとは?)
(姿勢革命とは?)
(減腔とは?)
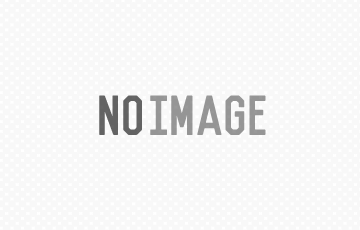 未分類
未分類
日本では胸腔、腹腔が狭まると、内臓機能が落ちると勘違いされてきた。
胸腔、腹腔が狭まると、内臓同士がぶつかり合って内臓の機能が低下すると今でも思われている。
「だから、背筋を伸ばし胸を張って胸腔腹腔を拡げて内臓機能を良くしましょう!!」
と言っている。
本当なんだろうか?
イタリア人は背中を丸めてリラックスして、食事をしている。
胸椎は後弯で、腰椎も後弯である。
パンダもゴリラも餌を食べる時には座って背中を丸くして食べています。
なぜなら背中を丸くしてリラックスした時のほうが副交感神経優位で、
内蔵への血流が良くなり、内臓機能がUp するからです。
逆に背筋を伸ばして胸を張ると、交感神経優位になり、内臓への血流は低下し、内臓機能も落ちます。
海外の本(オステオパシーでは、上半身の後ろは背骨で支え、前は内臓で体を支えると書いてあります。
骨盤の上に胸郭を石を積むように置くと、自然と腹腔は潰れます。
前かがみになるように内臓を潰すのではなく、上半身の重みと重力を鉛直にお腹に載せる感じです。
また、横隔膜呼吸と共に上下しています。胃や腸は蠕動運動をして消化をしています。
内蔵は横隔膜の動きに連動してお腹の中で上下したり回旋しているのです。
大腸(上行結腸や下行結腸)は横隔膜と連動して、深呼吸時には10センチも動くそうです。通常の呼吸でも3センチぐらいは動きます。
この横隔膜の動きが内臓を刺激して内臓機能をUPするのです。
しかし。胸腔、腹腔を拡げると、内臓の間にスペースが生まれ、横隔膜が上下しても内臓同士がぶつかり合い、刺激しあうことが少なくなり、内臓機能は低下します。
また、内臓間にスペースができすぎると胃下垂などにもなりやすくなります。
腹腔を潰すと内臓機能が低下すると勘違いされたのは椎間板ヘルニアなどが原因だったのではないでしょうか?
神経を圧迫すると痛みやしびれが出るので、内臓同士も圧迫されると、機能低下や病気になると勘違いされたからかもしれません。
局所的な神経や血管の圧迫は機能低下を生みますが、生理的な臓器同士の圧迫は逆に刺激になり、内臓の機能をUPさせます。
本ら、座位の時は背中を丸くするのが自然であって、副交感神経優位な姿勢です。
胸腔、腹腔に重力が乗ることで内臓機能はUPします
>>>>>>セミナー情報<<<<<<<<<
東京 2月16日
■4DS新着情報
(4DSとは?)
(姿勢革命とは?)
(減腔とは?)