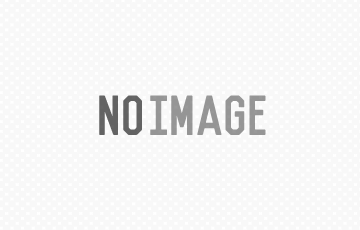幼虫や胎児などの無脊椎生物は、腔で、重力下で生存しています。
建物でいうと枠組み工法です。幼虫や胎児では、大きい動きは、屈曲伸展と限られています。
脊椎動物は、進化の過程で多様な動きを実現させるために、脊椎や関節が生まれました。
それにより側屈、トランズの動きが可能に、蛇のような蛇の動きが可能になりました。
枠組み工法は、軸組み工法より耐久性が二倍いあるといわれています。
しかし、枠組み工法では、動きが存在しにくい欠点があります。
柱で形成される軸組み工法は、横揺れが非常に容易にできます!!
横揺れは、脊椎動物に、非常に重要な動きと移動の手段になります。
脊髄動物は軸組み工法に柔軟性のある腔(軟部組織)の壁がついた構造となり、多様な動きと、耐久性を得ました。
強度は枠組み工法よりも柔軟性のある軸組み工法が人間の立位においては、優れたものになります。
発生学、機能構造学的に、なぜ脊椎が必要になったかを考えれば、わかることです。
耐久性を維持し、動きを多様化するためには、動きのある生物の軸工法は必要になったのです。

100年前の理論は、腔や筋肉で立って姿勢を維持していると本に書いてあります。
しかし理想的な姿勢は筋肉を最小限にしか使わず、ただ無機質な背骨の積み木が靭帯で固められ、重なって存在するだけなのです(^^♪
昔ながらの理論を信じているために、、日本のアスリートは人一倍努力しても報われない!!
体幹や腔をつぶして、体を動かせば、パフォーマンスは倍増するでしょう(^^♪
4DSでは、量子力学の空間技から、生理学、解剖学、生体物理学まで、サルでもわかるように解説していきます(^^♪