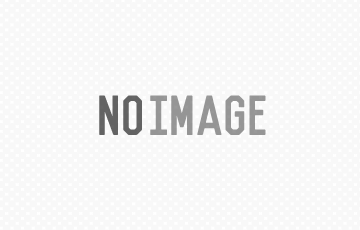治療家は、施術ごとに痛みなどの症状の軽減、消失を目指す。
これを認識療法という。
いくつもの手法が組合させるが主に下記が多い。
a,交感神経優位にして、痛みを患者させない。(セミナーなどで緊張していると痛みを感じなくなる。)
b,運動軸を変える。(同じ運動をしているようで、、まったく違う筋肉を使っている。)
c,関節運動を連動させる(痛い動きを連鎖運動で、補助する。)
d,痛みの意識を他に移す。(眼球運動に集中させて、痛みがなくなる。)
e,痛みの強い刺激で、従来の痛みを消す。(鍼灸)
f,運動する刺激で、痛みの刺激を打ち消す。
fの神経学的な解説
神経線維の直径が大いいほど、脳への伝達が速い。
筋や腱の神経線維の直径は15で、痛みの神経線維は0.5である。
神経線維の直径が大きいほど刺激に対する閾値が低い。
すなわち脳に伝わりやすい。
筋や腱を動かし刺激すると、痛みの脳への伝達をブロックし、痛みを感じなくなる。
例えば、首を後ろに反るのが痛い人が、手首を屈曲伸展すると、首を反っても痛くなくなる。
上のc、d、fの要素が加わっている。
セミナー会場で大勢の前で、これを行うと、aの要素が加わる。私もよく利用する。(^^♪
4DSでは、手技療法で、機能構造を整え、認知療法で、脳への伝達回路を改善させる!!
| 求心性神経線維の分類 | ||||
| 分類 | 種類 | 直径(μm) | 伝導速度(m/s) | 機能(例) |
| Ⅰa | 有髄 | 15(15~20) | 100(72~120) | 筋紡錘の環らせん終末 |
| Ⅰb | 有髄 | 15(15~20) | 100(72~120) | 腱器官 |
| Ⅱ | 有髄 | 9(6~12) | 50(36~72) | 筋紡錘の散形終末・皮膚触圧覚 |
| Ⅲ | 有髄 | 3(1~6) | 20(6~36) | 温痛覚→体性痛 |
| Ⅳ | 無髄 | 0.5(<1) | 1(0.5~2) | 痛覚→内臓痛 |